

![]()
ダムを意図的に壊すという、これまでの常識を覆すチャレンジが、群馬県みなかみ町にある約1万ヘクタールの国有林内の治山ダムで行われました。治山ダムは人間にとっては大雨による被害から命や家屋を守ってくれる壁ですが、その渓流で暮らす生きものにとってみれば、本来自由なはずの行き来をはばまれるもの。林野庁関東森林管理局と日本自然保護協会、地元住民グループの三者が2004年に結成した「赤谷プロジェクト」では協議や調査を重ねた上、「ダム撤去」という勇気ある決断を実行に移しました。生物多様性の復元を目指し、まったく前例のない取り組みが今、動き始めたのです。
目次へ移動 温泉地の近くで
 撮影 茅野恒秀
撮影 茅野恒秀
今回訪れた国有林「赤谷の森」は、新潟県との県境に近い群馬県みなかみ町にあります。最寄りの上毛高原駅までは、東京駅から新幹線で1時間半弱。車でも関越道経由でほぼ同じくらい、と都内から比較的交通アクセスの良い場所です。道中には湯宿温泉に猿ヶ京温泉、川古温泉、法師温泉など雰囲気の良い温泉地がいくつもあるので、温泉好きの人は、もしかしたら足を運んだことがある場所かもしれません。
そんな観光地の近くで、生物多様性復元を目指したとても先進的な活動が行われているのです。皆さんはご存じでしたか?
 一般的には30-40年ほど前に降った雨・雪が地中で温められ、湧き出したものが温泉。豊かな森林がもたらしてくれます(法師温泉・長寿館) 撮影 茅野恒秀
一般的には30-40年ほど前に降った雨・雪が地中で温められ、湧き出したものが温泉。豊かな森林がもたらしてくれます(法師温泉・長寿館) 撮影 茅野恒秀
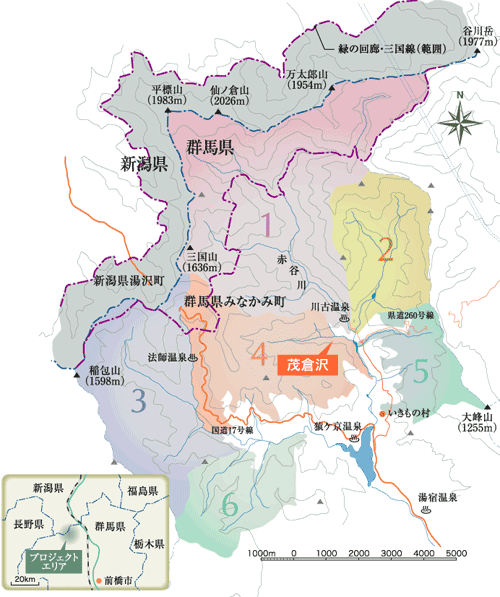 赤谷プロジェクトマップ
赤谷プロジェクトマップ
様々な表情を持つ赤谷の森はおおまかに6つのサブエリアにわけられています。管理のテーマもそれぞれの特性に合わせて考えられたものです。
今回私が取材したダム撤去プロジェクトが進む茂倉沢は、エリア4に属します。赤谷プロジェクトの中では、渓流環境復元ワーキンググループが担当しています。
目次へ移動 現場を見る・感じる
昨年11月10日、ダムが撤去された現場での合同見学会に参加しました。これまで防災目的で、自然の中にコンクリート製のダムを建設することは数えられないほど繰り返されてきましたが、それが公共事業によって日本で初めて「なくされる」歴史的な現場をじかに見たいと思ったことがきっかけでした。
今回撤去対象となったのは、利根川水系の赤谷川の支流、茂倉沢の2号ダム。下流側から数えて2番目にあるダムです。
 工事前の2号ダム
工事前の2号ダム
 昨年10月26日に工事が始まり、幅28メートル、高さ9メートルのダムの中央部、幅約8.6メートルが取り除かれました 撮影 茅野恒秀
昨年10月26日に工事が始まり、幅28メートル、高さ9メートルのダムの中央部、幅約8.6メートルが取り除かれました 撮影 茅野恒秀
昭和20年から30年代に茂倉沢本流と支流には、合わせて17の治山ダムがつくられました。直接的なきっかけとなったのは、1947(昭和22)年に発生したカスリーン台風です。カスリーン台風は全国で1,000人以上の死者を出しましたが、群馬県では最大の592人が死亡。激しい土石流がもたらした痛ましい悲劇は、60年以上経った今でも語り継がれるほどです。当時は戦中戦後の資源不足の影響で山に木がほとんどなく、そのことが被害に拍車をかけ、茂倉沢上流部辺りでも大きな崩落が起こりました。あの八ッ場ダムも、計画のきっかけはこのカスリーン台風の襲来でした。
目次へ移動 治山ダムってどんなダム??
「ダム」とひとくちに言っても、実はいろいろな種類があります。洪水調節などを目的につくられる「治水ダム」、水の確保や発電などに利用される「利水ダム」、それらの目的をあわせ持った「多目的ダム」、土砂災害を防ぐためにつくられる「砂防ダム」などが主なものとしてあげられます。
今回撤去されたダムは、「治山ダム」と呼ばれます。一般の人はあまり聞き慣れませんが、森林を管理する「森林法」に基づき、大雨が降ったときに山肌が崩壊しそうな渓流につくられます。 期待される防災効果は
治山ダムの建設目的は、簡潔に言えば、「山を治すこと」なので、森林が回復すればその使命はだいぶ果たしたことになります。全国の治山ダムに損傷や劣化も目立っていますが、これまでに撤去が意図的に行われたことはなく、逆に現在でも建設半ばの治山ダムが全国各地にあるのだそうです。
治山ダムは山深い渓流につくるため、多くの場合、移動してもらう人家などへの補償を伴いません。災害時の大きな土嚢(どのう)のような役割を果たすものなので、規模も小さめ。防災手段としてはつくりやすく、そのために全国の渓流を必要以上に固めてきてしまったと言います。渓流環境はダム設置で大きなダメージを受けますが、そのデメリットが表立って議論される機会はあまりありませんでした。
 川は例えれば、人の血液。よどみなく流れることで渓流環境の「新陳代謝」を促します 撮影 茅野恒秀
川は例えれば、人の血液。よどみなく流れることで渓流環境の「新陳代謝」を促します 撮影 茅野恒秀
目次へ移動 ターニングポイントにある治山事業
赤谷プロジェクトの構成団体である日本自然保護協会(以降、NACS-J)が発行する会報『自然保護』の特集記事「渓流環境の修復を考える」(2008年3・4月号)の中で、富山県立大短大環境システム工学科准教授の高橋剛一郎さんは、次のように書いています。
防災対象がなくなったり変化したところでは、安易にコンクリート製のダム設置を計画することを考え直すのはもちろん、見直し(補修や改修)などの際に、治山ダムの小型化や撤去などを検討することも十分可能であると思います。しかし、実際にはそれらが行われたことはほとんどありません(抜粋)。
高橋准教授は、時代とともに社会の考え方も、法(※)も変わってきていることから、従来の治山ダムを主体にした「治山」が時代のターニングポイントにあることを鋭く指摘しています。
※ 関連する法律には、第三次生物多様性国家戦略(2007年策定)や、失われた自然環境を取り戻すことを目指す自然再生推進法(2003年施行)などがある。また、山地から海まで土砂が運ばれないことで起こる河道や海岸の浸食を防ぐため、「流砂系」という新しいことばで土砂管理の方針転換を示した「流砂系の総合的な土砂管理」なども、従来のダムによる土砂遮断から、土砂を流すことに意識を向けていくことを示している
目次へ移動 沢を歩き、石ごろごろの道を行く
スパイクのついた長靴をお借りし、落ち葉をザクザク言わせながら道のりを急ぎます。途中、沢の中を歩くので、スニーカーなどでは濡れてしまいます。
 一歩一歩、足を「よいしょ」と持ち上げる感じで歩きます
一歩一歩、足を「よいしょ」と持ち上げる感じで歩きます
参加した関係者の皆が口をそろえて、「50年前とはだいぶ森林の様子も変わってきている」と言います。長い年月をかけ、山は豊かな森をようやく取り戻しつつあるのです。
 撮影 茅野恒秀
撮影 茅野恒秀
撤去された2号ダムより先に下流の1号ダムに着きました。コンクリートを覆う緑色のコケが設置からの年月を物語ります。沢の水がゆるやかに流れ落ちていました。
 撤去されたダムとほぼ同時期、同サイズでつくられた1号ダム
撤去されたダムとほぼ同時期、同サイズでつくられた1号ダム
撤去された2号ダムは、8年前の洪水で底抜けを起こし、土砂が流出。そのため、2号ダムまでの道のりに川の水はあまりなく、ごろごろとした石の道(専門用語では、堆砂敷<たいさじき>)が数百メートル続きます。
 長い堆砂敷。川は端の方を流れています
長い堆砂敷。川は端の方を流れています
いよいよ撤去された2号ダムの現場に着きました。
 ブレーカーで崩された跡がそのままになっていました
ブレーカーで崩された跡がそのままになっていました
見学会の時点では、底にまだ数メートルの土砂が溜まっていて、水は撤去された中央部でなく、パイプを使って底抜けを起こした右壁下側にう回させてありました(仕上げ工事は11月末に完了)。
通常は作業道をつくって重機を入れるそうですが、今回は小さなモノレール道を設置して資材の運搬をしました。工事はクマタカの営巣が確認されたことで当初の予定を遅らせましたが、モノレールも周りの環境に影響を与えない配慮とのこと。
 資材を運ぶミニモノレール
資材を運ぶミニモノレール
見学者からは、ダムの両袖が残されていることに質問が集中しました。「これでは、一般の人はダムを撤去したと思えないのでは...」と厳しい見方も。実際には、両袖まで撤去するのが理想なのですが、土砂の過剰な流出や山腹の崩壊リスクを考慮し、第1段階としては中央部撤去としたそうです。
 撤去ダム前に集まる参加者
撤去ダム前に集まる参加者
例えば、サケが産卵時に川を上がるためなど、動物や魚の行動範囲を邪魔しないよう櫛(くし)状のスリットを入れる「スリットダム」や魚道などは、全国に先例がありますが、基礎部分までとってしまう大胆な試みは全国初。NACS-J職員で、プロジェクトを長く担当している茅野恒秀さんは、「底の部分が横断するかどうかが、ダムであるかどうかの判断基準。今回は基礎部分もすべてコンクリートをとってしまったから、ダムではない」と回答していました。基礎が残ると、水面のわずか上を飛ぶ昆虫などには、生息環境に影響が出ます。
「川は川につくらせる」、印象に残った茅野さんのことばです。ダムを撤去すると、水も土砂も自由に流れるようになり、川そのものが川の流れをつくるというパワーを持つようになります。撤去の一番のねらいもそこにあります。
目次へ移動 難しい防災との両立
2号ダムを見学した後、再び1号ダムとの中間くらいの地点に戻ります。ここには、洪水が起きた場合の水や土砂の流れをコントロールする措置として、新たに「保全工」がつくられました 。
 両サイドに見えるコンクリートの壁が保全工。2号ダムと1号ダムのちょうど中間くらいにあります
両サイドに見えるコンクリートの壁が保全工。2号ダムと1号ダムのちょうど中間くらいにあります
中央部分を11メートル空け、左右に低めのコンクリートの壁をゲートのようにつくってあります。大雨が降って、土石流が発生した場合の激しいがけ崩れを想定しています。今後モニタリングを続け、なくても安全に山を保てることがわかれば、「撤去していく」とのこと。
赤谷プロジェクト内に渓流環境復元を担当するワーキンググループが発足したのは2005年でした。その際、専門家の先生による組織「新治地区茂倉沢治山事業全体計画に関する検討委員会(委員長:太田猛彦・東京大学名誉教授)」との連携体制がつくられました。防災面の検証には、専門的な調査や知識が欠かせませんから、こうしたバックアップもダム撤去の根拠を裏付けています。
現在では森がだいぶ回復したこと。万が一、土石流が流れ出しても周囲に民家がないこと。下流に被害を食い止める1号ダムがあり、その上流でダム撤去の技術開発に取り組めること。これらの条件がそろい、ようやくGOとなった今回のプロジェクト。目的は渓流環境を元に戻し、生物多様性を回復させることなのですが、防災と両立させることは、なかなか難しい判断であることをうかがわせます。
目次へ移動 意思決定の新しい形
治山ダムの一部撤去を「ささやかな試み」と感じる人もいるかもしれません。でも、これまで自然の中につくられるばかりだったコンクリートの建造物を国もかかわって、意図的に壊すということ。つまり、国税でその作業を行うということですが、その意思決定が地域の人々も交えた議論とコンセンサスの上になされたことは、とてつもなく大きな一歩だと思いました。
では、この意思決定の場はどのように形成されたのでしょうか?
目次へ移動 スタートは必然的に
赤谷プロジェクトの正式名称は、「三国山地/赤谷川・生物多様性復元計画」と言います。長い正式名を持ったこのプロジェクトは、林野庁関東森林管理局とNACS-J、赤谷プロジェクト地域協議会の間で2004年3月30日に結ばれた協定に基づいて行われています。
地元には、バブル期に浮上したスキー場やダム計画への住民の反対運動が下地としてありました。NACS-Jとの縁もそのときからだと聞きます。森はとびっきりおいしい水や豊かな温泉を恵んでくれるばかりでなく、絶滅危惧種であるイヌワシやクマタカ、ツキノワグマ、ニホンカモシカなどのすみかであることも運動を展開する中で明らかになっていきました。
 (左上)ツキノワグマ、(右上)クマタカ、(左下)カモシカ、(右下)イヌワシの親子
(左上)ツキノワグマ、(右上)クマタカ、(左下)カモシカ、(右下)イヌワシの親子
イラストは2005-2007年まで赤谷の森を担当していた林野庁の森林官・平田美紗子さん
2000年、バブル崩壊の流れにも後押しされ、スキー場もダムも開発中止になります。しかし、住民の皆さんは、そこで「終わり」ではなく、守られた自然をもっとよくする仕組みをつくってみたいと感じるようになっていました。NACS-J側も、評価方法がとても難しい生物多様性を取り戻していく過程を世の中に見せたいという思いから、そのモデルケースにふさわしい場所を探していました。両者の思いがうまく重なり合い、赤谷の森一帯の国有林の共同管理を林野庁に持ちかけてみようということになったのです。
担当局・関東森林管理局の反応は思いのほかよく、準備会議の開催がスムーズに決まりました。それまで国有林の管理は国がリードして行ってきましたが、赤谷の森の決めごとには地域協議会とNACS-Jのメンバーを交えて開く「企画運営会議」での了承が必要になりました。法律上の管理者は現・関東森林管理局ですが、局は計画に赤谷プロジェクトで話し合った事柄を反映させると協定で約束したのです。
重い腰を上げた林野庁の思い切りのウラには、国有林を巡る時代の変化があります。戦後から生産してきた木材の価格が70年代に暴落。人工林の育成に力を入れてきた従来の方針に行き詰まりが見え、2001年に森林・林業基本法が見直されました。そこでは、森林がもともと持っていた能力の数々、例えば、水や土壌を守ったり、人と共生したり、資源として循環していくといった役割により力を入れていくことが決められました。
それまで林野庁とNACS-Jは国有林伐採で意見がぶつかり合うこともあり、新聞記事などでは、両者の「歴史的な和解」と書かれたりもしました。関東森林管理局・赤谷森林環境保全ふれあいセンター所長の田中直哉さんは、「川古ダム(国交省が計画)に反対する一連の住民運動も見ていたし、未来の森づくりは皆でやっていかなければといった機運が高まっていたのだと思います」と当時を振り返ります。
目次へ移動 森を取り巻く多様な声
赤谷プロジェクトにはコア団体の構成メンバーの他に、おそろいの帽子が目印のボランティアサポーターが関東一円に50、60人ほどいます。赤谷の森には、かつて人工林の苗床を育てていた作業小屋の建物を再利用した拠点「いきもの村」があります。月始めの週末に開かれる「赤谷の日」には、有志がここに集まって森の生物を調査したり、地域と接点を持ったり、昔ながらの炭焼きに挑戦したりしています。森を取り巻く多様な声が、プロジェクトをより豊かなものにしています。
 地元・猿ヶ京小の子どもたちが「いきもの村」周辺で遊びながら学ぶ様子を平田さんがイラストでまとめたもの
地元・猿ヶ京小の子どもたちが「いきもの村」周辺で遊びながら学ぶ様子を平田さんがイラストでまとめたもの
「ものを考える仕組みとか、かかわる姿勢とか、どうやって合意をとるのかとか、何かが起きたときに何を考えればそれをきちんと考えることになるかとか、そういうプロセス自体、モデルだと思っています」、茅野さんはそう言います。
 NACS-Jの茅野さん
NACS-Jの茅野さん
治山ダム撤去については前例がないことから、評価技術もありません。生物多様性についても判定基準はないので、これから、絶滅危惧種の生物はもちろん、渓流沿いの森林や土砂の流出状況、昆虫や魚などについても丁寧にモニタリングを続け、データを収集していきます。5年後、10年後に「あれは大きな一歩だったと言われるようにしたい」というのが、かかわっている皆さん共通の願い。全国各地で老朽化が進み、改修時期を迎える治山・砂防ダム管理のモデルケースとなることを目指しているのです。
目次へ移動 人と森とのかかわりをヒントに
猿ヶ京ホテルの大女将で旧新治村(現みなかみ町)の民話研究第一人者である持谷靖子さんは、明治生まれの地元のおばあちゃんからこんな話を聞いたと言います。
 森の上空を飛ぶイヌワシ 撮影 高野丈
森の上空を飛ぶイヌワシ 撮影 高野丈
ある家の嫁が5月の田植えの時期に弁当をこしらえて田んぼに入った。赤子を置いて作業を始め、田植えしちゃ子どもの様子を見ていたが、つい夢中になって目を離したすきに、大きなワシが連れ去ってしまった。
「オラ(私)ガ(の)アカッコー(赤ちゃん)」「オラガアカッコー」と、嫁は泥だらけの足で後を追いかけたが、子どもは見つからない。「オラガアカッコー」と泣くうちにその嫁はついにカッコーになってしまった。
「ほんとに今でも5月になると田んぼに探しに来るのよ、すごく低空飛行でね」、持谷さんは言います。霜降り模様をした足を持つカッコーを、泥だらけの足で子どもを探す母の姿に重ねているのです。赤子を連れ去ったワシがイヌワシかどうかは、詳しく語られていませんが、大型のワシが日々の暮らしの中でどのようにとらえられていたか、その情景まで浮かんでくる話です。
茅野さんは、例えば「イヌワシがこの地域の人々にとってどういう存在だったのかを考えることが、この地域をどう守っていこうかという力につながる」と言います。地元の人と森とのかかわりを丁寧にひもとき、尊重している姿が印象的でした。
今後の課題は「昔の森に戻したい」という地元の願いをかなえていくこと。地域協議会は、まだ 町も積極的に参加していないため、「地域の代表と言っても、ほんの一部」と考えています。まだまだこれから、なのです。
目次へ移動 まとめにかえて~防災の時間軸
さて、今回の見学会に参加し、ダム撤去を「伝えること」の難しさを肌で感じました。生物多様性を取り戻すと言っても、その効果はすぐには目に見えて現れませんし、その「効果」とは、人間にとってのわかりやすいメリットではないからです。例えば、「明日の紙面に載せる」といったスピードで事業の概要を正確に伝えることはとても難しい、そう感じました。
森がなくなった場所にダムがつくられた
→その後、長い時間をかけて再び森がつくられた
→ダムがなくても大丈夫ではないかという状態になった
今回のダム撤去はそうした長い時間軸をたどって決断されたものですが、大事な流れだと感じました。私たちは普段、なかなかそうした余裕幅を持って「防災」をとらえることをしていないように思い、はっとしたのです。つまり、私たちと森とのかかわりを大切に考えた上での持続可能な「防災」のあり方を、です。
 工事完了後の2号ダム 撮影 茅野恒秀
工事完了後の2号ダム 撮影 茅野恒秀
「赤谷プロジェクトのゴールは設けられない」と話していた茅野さん。かかわっている誰もが、森の再生、そして、生物多様性の復元には、自分の人生を超えた時間を想定していました。まずは、その時間軸を共有すること。それが第一歩なのだと思いました。自然の声に繰り返し耳を傾けては、細かな合意形成を重ねていく―。ときにはもどかしいほどの地道なプロセスこそが、赤谷プロジェクトのパイロット・プログラムとして使命なのだと私も感じ始めていました。
 撮影 出島誠一
撮影 出島誠一
関連リンク
林野庁関東森林管理局
日本自然保護協会(NACS-J)
赤谷プロジェクト
岩井光子 略歴
地元の美術館・新聞社を経てフリーに。2002年、行政文化事業の記録本への参加を機に、地域に受け継がれる思いや暮らしに興味を持つ。農家の定点観測をテーマにした冊子「里見通信」を2004年に発刊。地球ニュース編集スタッフ。高崎在住。
取材・執筆:岩井光子
写真:佐々木拓史(Think the Earthプロジェクト)
写真提供・協力:日本自然保護協会(NACS-J)